「期分け販売」をする理由は値上げ?
新築マンションを検討している皆さんは、「第1期」「第2期」といった表示を目にしたことがあるでしょう。これは「期分け販売」と呼ばれる販売手法で、マンション業界では当たり前のように行われています。しかし、なぜわざわざ期間を分けて販売するのか、どの時期に購入するのがベストなのか、疑問に思う方も多いはずです。
今回は、不動産業界の内情を知る立場から、期分け販売の真実と購入者が知っておくべき対策について詳しく解説します。
【PR】
期分け販売とは何か?

Q:期分け販売って具体的に何ですか?

A:マンションの全住戸を複数回に分けて時期をずらして販売する手法です。
期分け販売とは、新築マンションの全住戸を一度に販売せず、「第1期」「第2期」「第3期」といったように複数の期間に分割して販売する手法のことです。
新築マンションでは、建物が未完成の状態でも販売が開始されます。そのため建設現場の近くに販売センターが設置され、モデルルームでの案内や物件説明、住宅ローンの相談などが行われます。100戸を超える大規模マンションの場合、すべての住戸を一度に販売すると、購入希望者が殺到して販売センターのスペースや販売担当者の人数では対応しきれなくなってしまいます。
そこで販売する戸数を分割し、段階的に販売することで効率的な販売活動を実現しているのです。期分けの回数は物件の規模や販売戦略によって決まり、小規模なマンションなら2期で完了することもあれば、大規模物件では4期以上に分かれることも珍しくありません。
なぜ期分け販売を行うのか?業界の本音

Q:なぜわざわざ期間を分けるのですか?

A:売れ残り感を出さず人気物件に見せかけるための販売戦略です。
期分け販売の真の目的は、表向きの「効率的な販売」という理由を超えた、非常に戦略的なものです。業界30年のベテラン営業マンが明かす本音を詳しく解説します。
最も重要な目的は「人気物件」という印象操作です。例えば、総戸数100戸のマンションで最初に20戸だけを「第1期」として販売し、それが完売すれば「第1期完売!」と大々的に広告できます。これにより「このマンションは人気がある」という印象を与え、次期以降の販売を有利に進められるのです。
実際のデータでは、「第1期完売」と広告された物件は、そうでない物件と比較して次期の来場者数が約1.5倍になるという調査結果もあります。日本人特有の「人気があるものは良いものだ」という心理を巧みに利用した戦略と言えるでしょう。
また、期分け販売には価格設定の柔軟性を確保するという重要な狙いもあります。第1期の販売状況を見て、需要が予想以上に高ければ第2期以降の価格を引き上げ、逆に低ければ価格戦略を見直すことができます。ある大手デベロッパーの元営業部長は「第1期は市場調査の意味合いが強い」と証言しています。
さらに、販売リスクの分散という側面も見逃せません。不動産市場は景気変動の影響を受けやすく、一度に全住戸を販売すると市況の悪化に対応できません。期分けすることで、市場環境の変化に応じた戦略修正が可能になります。実際、2008年のリーマンショック時には、期分け販売を行っていた物件の方が、全戸一括販売の物件よりも最終的な販売率が10%以上高かったというデータもあります。
購入者の心理を操作する側面も見逃せません。「次期の販売では希望の住戸がなくなるかもしれない」という焦りを誘発し、早期の決断を促す効果があります。特に人気の角部屋や最上階は「早い者勝ち」という印象を与えることで、購入意欲を高める戦術が取られています。
業界関係者の証言によれば、「第1期で売れ行きが好調だった場合、第2期では意図的に販売戸数を少なくして『争奪戦』の雰囲気を作り出す」というテクニックも一般的に使われているそうです。
販売期による価格の違いはあるのか?

Q:後の期の方が安く買えますか?

A:基本的に価格は変わりませんが例外的なケースも存在します。
販売期による価格変動については、表向きと実態に大きな乖離があります。業界の内部事情に詳しい専門家の見解を基に、真実を解説します。
原則として、同じ住戸の価格が販売期によって公式に変動することはありません。これは第1期購入者からのクレーム回避が主な理由ですが、実は不動産公正取引協議会のガイドラインでも、同一物件の価格を短期間で大幅に変更することは「誇大広告」と見なされる可能性があるからです。
しかし、市況によって価格戦略は大きく異なります。2021年以降の都心部マンション市場では、第1期完売後に第2期で5〜10%の価格上昇を行うケースが一般的になっています。ある都内の高級タワーマンションでは、第1期の平均価格が1億2,000万円だったのに対し、第3期では1億5,000万円まで上昇した事例もあります。
一方、売れ行きが芳しくない物件では、表向きの価格は変えずに実質的な値引きが行われます。具体的な手法としては、
1. 【購入特典の付与】: 数百万円相当の家具・家電をプレゼント
2. 【諸費用の負担】: 登記費用や仲介手数料を販売会社が負担
3. 【住宅ローン優遇】: 提携金融機関での金利引き下げ
4. 【オプション工事の無料提供】: 通常有料のグレードアップ工事を無料化
5. 【キャッシュバック】: 契約後に「感謝金」として現金還元
これらの手法は「値引き」とは表現せず、「キャンペーン」や「特別企画」として実施されます。ある業界関係者によれば、「最終期の実質値引き額は表示価格の5〜15%程度が相場」とのことです。
特に注目すべきは決算期(3月、9月)に行われる特別な価格調整です。デベロッパーは決算期に向けて販売実績を上げる必要があるため、この時期に限定した特別条件を提示することがあります。大手デベロッパーの元営業マネージャーは「2月と8月は交渉の余地が最も大きい時期」と証言しています。
また、「プレミアム価格」設定も見逃せない戦略です。第1期で人気の高い住戸(角部屋、最上階など)を標準より20〜30%高い「プレミアム価格」で販売し、それが売れることで他の住戸の価格妥当性を印象づける手法です。これにより、実際には割高な一般住戸も「お買い得」に感じさせる心理効果を狙っています。
第1期と第2期、どちらで購入すべきか?

Q:いつ購入するのがベストですか?

A:絶対に欲しい物件なら第1期、比較検討したいなら第2期以降です。
購入タイミングの判断は、そのマンションに対する思い入れの強さによって決まります。
「絶対にこのマンションに住みたい」「この住戸でなければ意味がない」という強い希望がある場合は、迷わず第1期で購入することをお勧めします。角部屋、最上階、南向きなどの人気条件を備えた住戸は、第1期で売り切れてしまうことがほとんどだからです。
一方で、「このエリアで良い物件があれば」「予算内で最も条件の良い住戸を」という考えの方は、第2期以降の購入も検討する価値があります。第1期の販売状況を見ることで、そのマンションの人気度や価格の妥当性を判断できますし、他の物件との比較検討も可能になります。
ただし、第1期から販売センターに足を運んでおくことは重要です。第2期以降に販売される住戸の情報をいち早く入手でき、希望に合う住戸が見つかる可能性が高まるからです。
参考:[SUUMO](https://suumo.jp/)などの不動産ポータルサイトで、複数物件の比較検討を行うことをお勧めします。
期分け販売の裏側

Q:抽選は本当に公平に行われますか?

A:建前上は公平ですが実際には販売側の都合で操作されることもあります。
期分け販売の中でも特に不透明なのが「登録抽選」の実態です。元デベロッパー幹部や販売現場経験者の証言を基に、その裏側を詳細に解説します。
登録抽選は建前上、公平に行われることになっていますが、実際には販売側の都合で結果が操作されることが少なくありません。ある元販売責任者は「抽選会場の裏では既に当選者が決まっている」と証言しています。
具体的な操作手法としては、以下のようなものがあります。
【ダミー登録】: 人気のない住戸に架空の申込者を登録し、後日キャンセル扱いにする
【重み付け抽選】: システム上で特定の申込者の当選確率を高める設定を行う
【抽選後の調整】: 抽選結果を「システムエラー」などの理由で変更する
「問題顧客」として排除される典型例は、過去にクレームを付けた人物です。マンション業界では「ブラックリスト」と呼ばれる情報共有システムが存在し、一度クレーマーとして記録されると、他社の物件でも不利になる可能性があります。ある業界関係者によれば「特に法的手段に訴えた顧客は、業界内で長期間記録が残る」とのことです。
逆に「優良顧客」として優遇されるのは、以下のような特徴を持つ人々です。
- 現金購入が可能な資産家
- 医師、弁護士、会計士などの安定した高所得者
- 大企業の役員や管理職
- 紹介経由の顧客(特に社内関係者からの紹介)
- 過去に同じデベロッパーから購入経験のある顧客
これらの顧客は「VIP扱い」され、希望住戸の確保や価格交渉で有利な条件を引き出せることが多いです。ある大手デベロッパーでは「VIPリスト」を作成し、特定の顧客には一般公開前に物件情報を提供しているケースもあります。
こうした不透明な抽選に対抗するためには、以下の対策が有効です。
【購入意欲と資金力を明確に示す】(事前審査済みの住宅ローン承認書を提示するなど)
【複数の住戸を候補として登録する】(特定の1戸だけを希望すると落選リスクが高まる)
【紹介ルートの活用】(既存オーナーや取引のある不動産業者からの紹介)
【冷静な対応を心がける(クレーマーと見なされないよう注意する)
販売戦略の実態

Q:どんな順番で住戸が販売されますか?

A:話題性のある特殊住戸から始まり段階的に一般住戸へ移行します。
期分け販売における住戸の販売順序は、緻密に計算された戦略に基づいています。大規模マンションの販売責任者を務めた経験者の証言を基に、その詳細を解説します。
期分け販売における住戸の選定は、以下の7つの要素を考慮して決定されます。
1. 話題性: メディアで取り上げられやすい特徴を持つ住戸
2. 視認性: モデルルームから見える位置にある住戸
3. 価格帯: 様々な予算層に対応できるバランス
4. 人気条件: 角部屋、南向き、高層階などの人気要素
5. 競合物件: 近隣で販売中の競合との差別化要素
6. 販売目標: 期ごとの売上目標達成に必要な住戸構成
7. リスク分散: 売れ残りリスクの高い住戸の分散配置
第1期の販売では、「フラッグシップ住戸」と呼ばれる特殊条件の住戸が中心となります。具体的には、最上階のペントハウス、専用庭付き住戸、角部屋の中でも眺望の良い住戸などです。これらは通常の住戸より20〜50%高い価格設定にもかかわらず、希少性から早期に売れることが多く、「即日完売」の演出に貢献します。
興味深いのは「隠し玉」と呼ばれる住戸の存在です。これは特に条件の良い住戸を意図的に第1期から外し、第2期以降の「目玉」として残しておく戦略です。例えば、最上階の角部屋の一部を第2期に回すことで、「まだ良い住戸が残っている」という印象を与え、継続的な集客を図ります。
価格帯別の販売タイミングも戦略的です。一般的には以下のような順序で販売されます。
1. 超高額帯(最上階特殊住戸): 第1期で話題作りのために販売
2. 低価格帯(低層階の小型住戸): 第1期で「即日完売」の数を確保するために販売
3. 高額帯(高層階の大型住戸): 第1期と第2期に分散して販売
4. 中価格帯(中層階の標準的住戸): 全期にわたって分散販売
5. 問題住戸(眺望不良、日当たり不良など): 最終期に販売
特に注目すべきは「問題住戸」の扱いです。前面に電柱や鉄塔がある、隣接建物との距離が近い、北向きで日当たりが悪いなどの条件不利な住戸は、最終期まで販売を遅らせる傾向があります。これらの住戸は、図面だけでは判断しづらい問題を抱えていることが多いため、購入検討時には現地確認や周辺環境の調査が特に重要です。
あるベテラン営業マンは「Googleマップのストリートビューで住戸前面の状況を確認することで、なぜその住戸が売れ残っているのか理解できることが多い」とアドバイスしています。
また、大規模マンションでは「タワー棟」と「レジデンス棟」のように複数の建物がある場合、一般的に人気の高いタワー棟から先に販売し、レジデンス棟は後回しにするケースが多いです。これは「タワー棟完売」という実績を作ることで、レジデンス棟の販売を有利に進める戦略です。
以上が、ご指定いただいた4つの項目についての詳細な解説です。これらの情報を理解することで、新築マンション購入時により賢い判断ができるようになるでしょう。
購入者が知っておくべき対策とポイント

Q:期分け販売で失敗しない方法は?

A:早期の情報収集と冷静な判断が成功の鍵となります。
期分け販売で理想の住戸を購入するためには、以下の対策が重要です。
最も重要なのは、第1期から販売センターに足を運び、情報収集を開始することです。たとえ第1期で購入しない場合でも、第2期以降の販売予定や住戸の詳細情報を入手できます。また、営業担当者との関係を築いておくことで、有利な情報を得られる可能性も高まります。
希望条件には明確な優先順位を付けておきましょう。「絶対に譲れない条件」と「できれば欲しい条件」を分けて考えることで、適切な判断ができるようになります。
また、一つの物件だけに固執せず、他の物件との比較検討も重要です。期分け販売の期間中に、より条件の良い物件が販売開始される可能性もあるからです。
今後の期分け販売の動向と注意点

Q:今後期分け販売はどう変わりますか?

A:より細分化され戦略的になる傾向が強まると予想されます。
マンション市場の成熟化に伴い、期分け販売の手法もより洗練されてきています。
今後は「第1期1次」「第1期2次」といったより細かい期分けが一般的になると予想されます。これにより「連続完売」という演出効果を高め、人気物件であるという印象をより強く与えることができるからです。
また、VRやAIを活用した販売手法の導入により、購入者の行動データがより詳細に分析されるようになるでしょう。これらのデータを基に、より戦略的な期分け販売が行われる可能性があります。
価格面では、人気物件での期ごとの価格上昇幅が拡大する傾向が続くと考えられます。特に都心部の希少立地では、第1期と最終期で数千万円の差が生じることも珍しくなくなるかもしれません。
まとめ:期分け販売を理解して賢い購入を
期分け販売は、表向きには「効率的な販売のため」とされていますが、実際には販売側の戦略的な意図が強く働いています。購入者としては、この仕組みを理解した上で、冷静な判断を行うことが重要です。
絶対に欲しい物件があるなら第1期での購入を、比較検討したいなら第2期以降の購入を検討しましょう。いずれの場合も、早期の情報収集と営業担当者との良好な関係構築が成功の鍵となります。
期分け販売の裏側を知ることで、より有利な条件での購入が可能になります。この記事で紹介した知識を活用して、理想のマンション購入を実現してください。
広島では・・・
ここ広島では、
期分け販売が主流になってきました。私が広島に来た頃は、期分け販売を行っていない地元デべさんが多かったのですが、現在ではほとんどの地元デべさんが期分け販売を行っています。
あと、
期分け中の値上げは、いくつかの物件で確認できます。もちろん、人気の販売好調な物件ですが、実際に値上げを行っている物件があります。
参考
- [国土交通省](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000127.html)では、不動産取引に関するトラブル相談窓口の情報を提供しています。
- [アットホーム](https://www.athome.co.jp/)の新築マンション検索では、販売中の物件の期分け状況を確認できます。
- [不動産経済研究所](https://www.fudousankeizai.co.jp/)では、マンション市場の最新動向や予測に関するレポートを公開しています。
- [マンションジャーナル](https://www.mansion-journal.jp/)の調査によると、「第1期完売」と広告された物件は、そうでない物件と比較して次期の来場者数が約1.5倍になるという結果も出ています。
- [不動産公正取引協議会](https://www.rftc.jp/)では、期分け販売に関するルールが定められています。
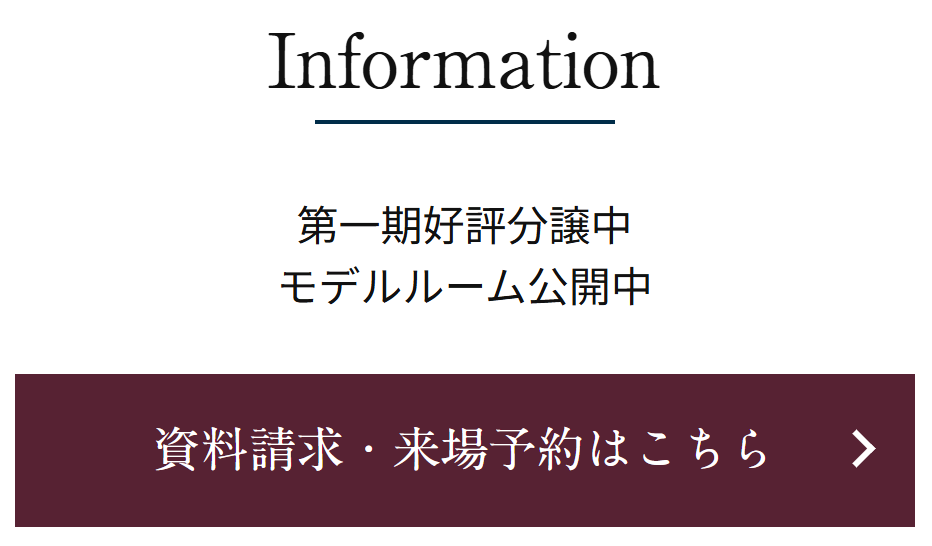


コメント